2025.11.04
ブログ
新着情報
「浸水・水害」補償の正しい使い方と火災保険でお金だけもらうのは違法?修理しない場合の注意点を解説
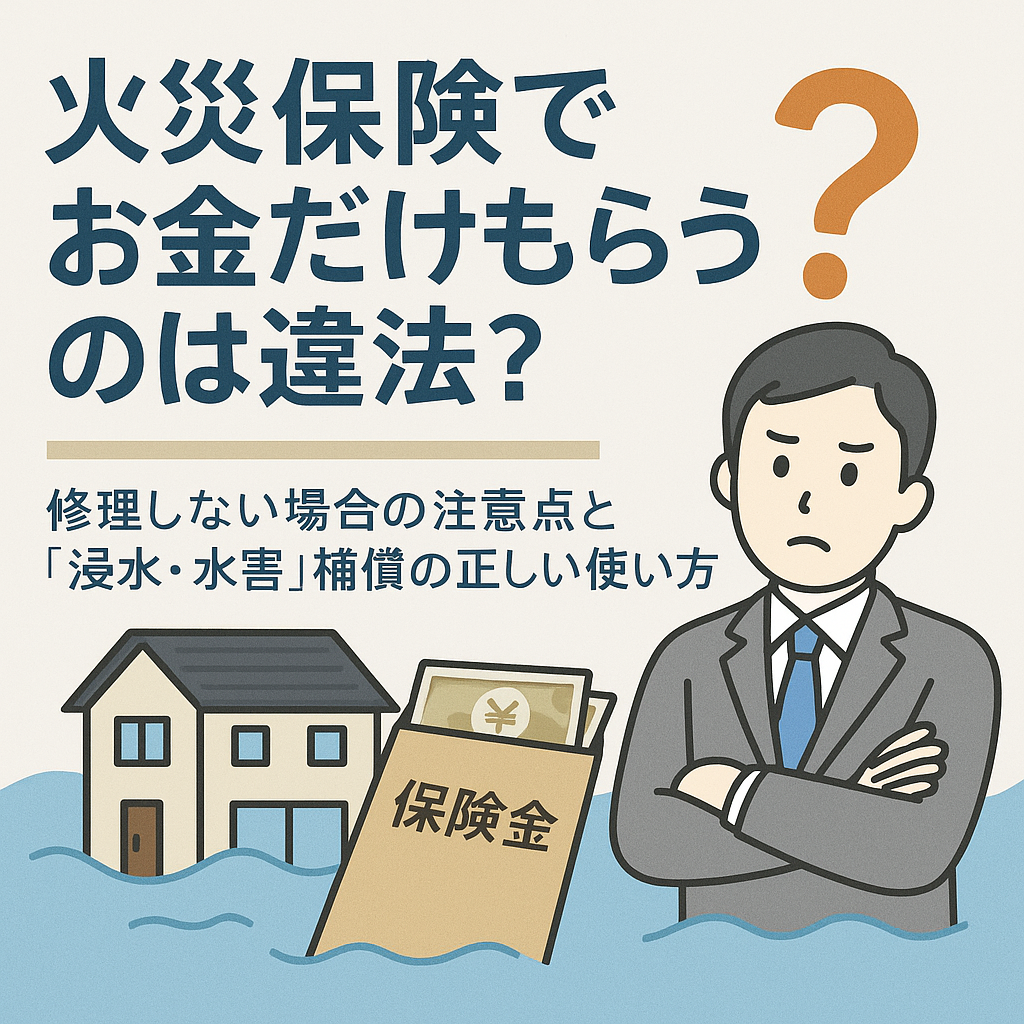
目次
- ○ 火災保険でお金だけもらうのは違法?修理しない場合の注意点と「浸水・水害」補償の正しい使い方
- ・🔹 火災保険で「お金だけもらう」のは違法?
- ・🔹 「浸水」や「水害」は火災保険で補償される?
- ・🔹 水災補償が支払われる条件
- ・🔹 補償の対象となるもの
- ・🔹 補償されないケースと他の補償の関係
- ・🔹 洪水・浸水時の火災保険金請求の流れ
- ・🔹 水害・浸水リスクを確認するには?
- ・🔹 まとめ
火災保険でお金だけもらうのは違法?修理しない場合の注意点と「浸水・水害」補償の正しい使い方
「火災保険でお金だけもらって修理しないのは違法なの?」
そんな疑問を持つ方が増えています。
実は、火災保険で受け取った保険金の使い道は基本的に自由です。しかし、「修理しないまま放置する」ことで、将来的に再申請ができなくなったり、損害が拡大してしまうリスクがあるのをご存じですか?
この記事では、
火災保険の水災(浸水・水害)補償の仕組み
「修理しない」とどうなるのか
補償対象・支払条件・申請の流れ
をわかりやすく解説します。
🔹 火災保険で「お金だけもらう」のは違法?
結論から言うと、火災保険で受け取った保険金を修理に使わなくても違法ではありません。
火災保険は「実際に発生した損害」に対して支払われる保険であり、使用用途に制限は設けられていません。
ただし、注意すべきは次の2点です。
同じ箇所の再申請ができなくなる
修理を行わずにそのまま放置しておくと、次回の災害で同じ場所が損傷しても「前回の損害が原因」とみなされ、保険金が支払われないケースがあります。
放置による損害拡大リスク
屋根や外壁などの破損を放置すると、雨漏りや腐食が進行し、結果的に修繕費が倍増することも。保険金の有効活用という意味でも、修理は早めに行うのがベストです。
※一部保険会社で復旧義務がある場合があります。
🔹 「浸水」や「水害」は火災保険で補償される?
火災保険の「水災補償」に加入していれば、次のような台風・豪雨・洪水・高潮・土砂崩れなどによる被害が対象になります。
✅ 水災補償で対象となる主なケース
・台風で川が氾濫し、床上まで浸水した
・豪雨で裏山の土砂が崩れ、建物に流れ込んだ
・集中豪雨によるマンホールの逆流で浸水
・記録的な大雨による高潮被害
🔹 水災補償が支払われる条件
火災保険で「水災」として補償されるには、次のいずれかの条件を満たす必要があります。
・建物や家財の損害額が再調達価額の30%以上であること
・床上浸水していること(フローリングや畳などの居住部分を超えて水が入った場合)
・地盤面から45cmを超える浸水があること
床下浸水だけでは原則補償対象外ですが、45cm以上または損害30%以上の被害であれば補償される可能性があります。
🔹 補償の対象となるもの
水災補償で対象になるものは、保険の契約内容によって異なります。
建物の場合の主な対象
・家屋本体(屋根・壁・床など)
・門、塀、垣、物置、車庫などの附属設備
・トイレ、浴室、システムキッチンなど固定設備
・電気・ガス・給排水設備、床暖房などの内装設備
家財の場合の主な対象
・家具、家電、衣類、自転車などの日常生活用品
・宝石や美術品など高額な品物(契約時に明記が必要)
💡注意:自動車は家財補償の対象外です。水害で車が損害を受けた場合は車両保険の適用となります。
🔹 補償されないケースと他の補償の関係
同じ「水」による被害でも、補償が受けられない場合があります。
・地震が原因の津波や土砂崩れ → 地震保険で補償
・マンション上階からの漏水・給排水トラブル → 「水ぬれ補償」で対応
・老朽化や経年劣化による雨漏り → 原則対象外(風災で屋根破損が原因なら対象)
・雹(ひょう)や雪による被害 → 「風災・雪災補償」で対応
🔹 洪水・浸水時の火災保険金請求の流れ
被害が発生したら、次の順番で手続きを進めます。
①保険会社へ連絡(契約者名・事故日時・場所・被害状況を伝える)
②罹災証明書を取得(消防署や自治体で発行)
③修理見積書や被害写真を準備して提出
④調査員が現地調査を実施
⑤保険金の金額確定 → 指定口座へ振込(通常3〜4週間)
保険金請求の時効は3年です。
時間が経っていても、一度保険会社に相談してみることをおすすめします。
🔹 水害・浸水リスクを確認するには?
自宅の水災リスクは、国土交通省が提供する「ハザードマップポータルサイト」で確認できます。
洪水・土砂災害・高潮の危険地域を地図で簡単に確認できます。
河川や海沿いだけでなく、都市部の「内水氾濫」リスクも確認可能です。
水害被害の多い地域では、水災補償を外さない方が安全です。
🔹 まとめ
火災保険の「水災補償」は、近年ますます増加している豪雨・台風・洪水・高潮・土砂災害といった自然災害に備えるための重要な補償です。
一度の浸水や洪水被害で住宅が受けるダメージは想像以上に大きく、床や壁、電気設備、家具などの修理・交換に数百万円単位の費用がかかることも珍しくありません。
そのような時、火災保険に「水災補償」を付帯していれば、これらの修繕費を大きく軽減できます。
一方で、「火災保険でお金だけもらって修理しない」という使い方を選ぶ方も増えていますが、これは違法ではないものの、
状況によっては同じ箇所が再度損害を受けた際に「前回の損傷を修理しなかった」と判断され、再申請できなくなるケースや雨漏りや構造部の腐食が進み、結果的に建物全体の価値が下がってしまうようなリスクを伴う可能性もあります。
火災保険は「いざという時に生活を立て直すための補償」です。
受け取った保険金をどのように使うかは自由ですが、資産価値を守り、今後の災害リスクを最小限に抑えるためには、適正な修繕や点検に使うことが最も賢明な選択です。
また、自宅の立地が河川や海に近い場合、あるいは低地にある場合は、ハザードマップを確認し、必要であれば水災補償の内容を見直すことも大切です。
保険の加入内容を定期的に点検し、建物の状況や住環境の変化に合わせて最適化することで、災害後の再建をスムーズに行うことができます。
火災保険は「万一の備え」ではなく、「生活を守るための資産運用ツール」でもあります。
正しい知識を持ち、必要な補償を確保することが、最終的に家族の安心と暮らしを守ることにつながります。
シェアする


